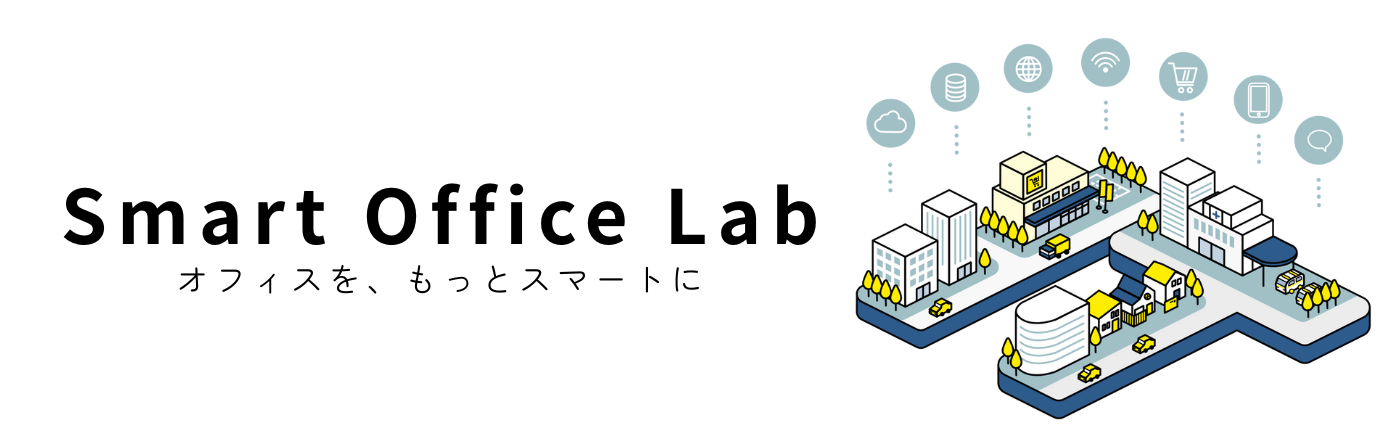オフィスの音環境は、集中力や快適性だけでなく、会議の機密性や来客時の印象、そして働く人の健康感まで左右する基盤となります。外から侵入する交通・工事音と、内側で生まれる会話・電話・タイピング音は、クレームや情報漏えい、ストレスの温床にもなるでしょう。
原因は単なる音漏れにとどまらず、壁・床・天井を介した振動の伝搬や、室内で増幅される残響にも潜みます。効果的な改善には、遮音・吸音・防振を薄く広く重ね、「音の性格」を設計することが重要です。まずはドアや窓のすき間封止、一次反射への吸音、床の静音化といったクイックウィンから着手し、計測とフィードバックで「測って直す」を回しましょう。
本記事では、その考え方と具体ステップを整理します。オフィスの音にお悩みの方は、参考にしてみてください。
オフィスで音を整える意味は?
オフィスの音問題は、生産性や快適性だけでなく、会議の機密性、来客時の印象、働く人の健康感にも関わる「基盤品質」です。外から入る騒音(交通・工事音など)と、内から漏れる音(会議・電話・タイピング音など)は、ともにクレームや事故情報の拡散、ストレス蓄積の引き金になります。
原因は、単純な音漏れだけではありません。壁・床・天井を伝う振動や、室内で反射して残る響き(残響)にも潜むため、現状把握と対策の切り分けが要となります。
防音対策のポイントは?
防音対策は大きく「遮音(音を通さない)」「吸音(反射を減らし響きを抑える)」「防振(振動の伝達を断つ)」の3要素で考えましょう。
遮音は壁・ドア・窓のすき間と材料の質量で決まり、吸音は天井・壁・デスク周りに柔らかい多孔質材を配置して残響を抑えます。防振は床下や機器の脚に防振材を介して固体伝搬を断つ考え方です。オフィスの音課題は複合的なので、どれか一つを盛るより、薄く広く重ねる方が費用対効果は上がります。
また、どこから音が通ってくるかも見極めるのが大切です。音の日常的な通り道は、①ドア隙間・建具、②窓やガラス面、③軽量壁・天井ふところ、④床配線口・OAフロア、⑤ダクトや共用廊下側のふところ、⑥机上面の反射です。
たとえば会議室のドアは面材自体の遮音より“隙間”がボトルネックになりやすく、先に扉周りのシールや厚手カーテンを足す方が効くケースが多い。デスク間の会話・タイピング音は、吸音パーテーションや卓上の吸音ボードで耳に届くエネルギーと反射を同時に落とすのが近道です。
効果的な対策方法
オフィスの音を軽減するためには、さまざまな方法があります。ここでは、導入しやすいものをいくつかピックアップしてご紹介しましょう。
防音グッズを使う
気軽に音を軽減するには、防音グッズを使うのが有効です。具体的には、次のような方法があります。
- ドア前に厚手カーテン・防音カーテン…扉の隙間から漏れる成分を一次遮断。会議室の声や物音などの抜けを減らす。
- 吸音パーテーション・卓上吸音ボード…デスク間の直達音と反射を同時に抑え、オンライン会議の相互干渉も軽減する。
- 壁面に薄型吸音パネル…打合せ卓の背面やコーナーに貼るだけで、響き(残響)由来の聞き取りづらさが改善する。
- タイルカーペットやマット…床反射を抑え、椅子や台車の転動音に対しても効く。
現在の環境によって、最適なものを選定するのが大切です。状況によっては、複数のアイテムを導入しても良いでしょう。
集中ゾーンとコラボゾーンを音で分ける
どこでも話せる環境は一見自由ですが、音は混ざると疲れを生みます。集中・通話・チーム作業・来客対応など、業務する内容によってゾーンを分けるのが有効です。
効果を高めるには、仕上げ材の吸音率やブースの配置で「音の性格」を変えるのがコツです。集中側は天井吸音・壁吸音+足元の敷設を厚めに、通話側は間仕切りブース+吸音パネルで狭域に音を閉じ込める。コラボ側はラウンジ・ハイテーブル等の可動家具で音の密度を散らしましょう。
防音対策のステップは?
効果的に防音対策を進めるためには、手順を踏むことが大切です。以下の流れを参考に、順番に実施していきましょう。
- 現状診断…騒音計測、残響推定、苦情ヒアリング。
- パイロット…1~2室を選び、壁・天井・机上の「薄い吸音+すき間対策」から。
- 効果検証…会議の聞き取りやすさ評価(主観アンケート+録音比較)、遠隔会議のエコー減少を確認。
- 拡張…ガラス面用の透明吸音、窓・ドアの追加遮音、床の静音化へ範囲を広げる。
- 運用化…通話ルール・ゾーニング・予約運用の標準化、年次での効果再評価。「測って直す」を前提にすると、投資の優先順位付けと社内合意形成が格段に進む。
一度にすべてのエリアを実施しようとすると、手間もコストも莫大となります。特に優先するべきエリアを絞って実践していくのがポイントです。
まとめ
音の悩みは、一気に完璧を目指さなくても問題ありません。小さく始めて、効き目のある対策を重ねれば、確実に働きやすさは上がります。
集中ゾーンは吸音を厚めにして静けさをつくり、通話はブースやパーテーションで狭く閉じること。コラボは可動家具や植栽で人と音をほどよく分散しましょう。加えて、通話はブース優先、オープン会話は短時間などの「音のマナー」をサインや予約アプリと連動して見える化してください。
月に一度の簡易計測やミニアンケートで手応えを確かめながら、足りない箇所に吸音・遮音を少しずつ増やしていくのもポイントです。今日できる一手から、静かで心地よいオフィスづくりを進めていきましょう。