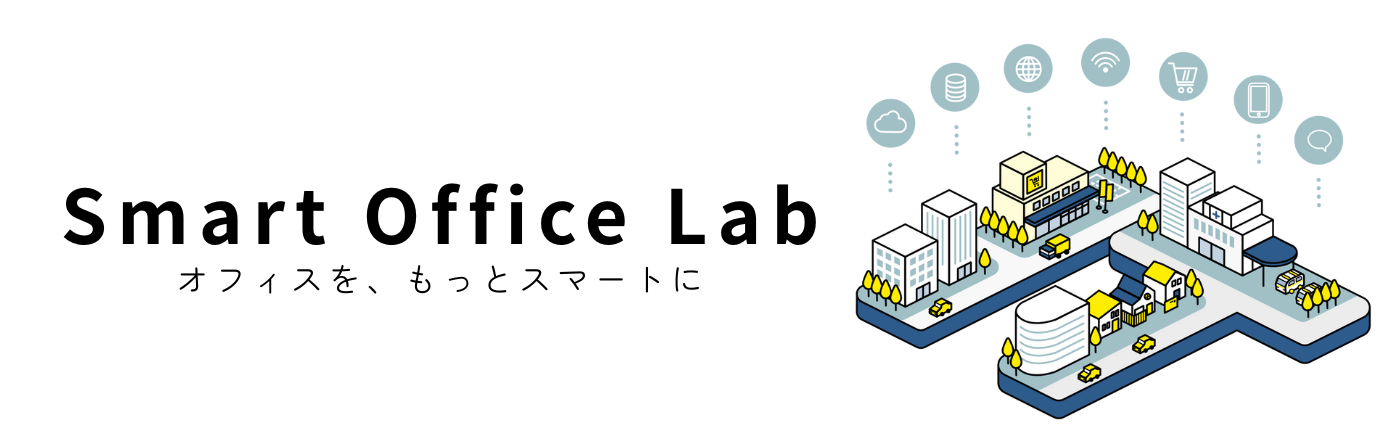近年、少子高齢化や共働き世帯の増加、そしてコロナ禍を経たリモートワークの普及により、従業員一人ひとりに合わせた柔軟な働き方が求められています。なかでも注目されているのが「時差出勤制度」です。
これは、所定労働時間はそのままに、出退勤時間のみをずらして働ける仕組みで、通勤ラッシュを避けたり、育児・介護と仕事を両立しやすくする効果があります。フレックスタイム制度と異なり、あらかじめ設定された複数の勤務パターンから選ぶため、柔軟性と管理のしやすさを両立できる点も特徴です。
本記事では、時差出勤のメリットや導入ステップを解説します。導入を検討している方は、参考にしてみてください。
働き方を柔軟にする時差出勤制度とは?
近年、少子高齢化や共働き世帯の増加、そしてコロナ禍を契機としたリモートワークの浸透など、労働環境は急速に変化しています。従業員一人ひとりのライフスタイルや事情に寄り添いながら、生産性を高める「柔軟な働き方」が企業に求められています。その中で注目されている制度のひとつが「時差出勤制度」です。
時差出勤とは、従業員が始業・終業時間をずらして働く制度で、勤務時間そのものは変えずに出退勤の時間帯を調整できるのが特徴です。例えば、通常9時始業の会社であれば、8時や10時などにずらして出社し、所定労働時間を確保したうえで終業時間も繰り上げ・繰り下げる形を取ります。
フレックスタイム制度と似ていますが、フレックスタイムが「一定期間内の総労働時間を満たせば勤務時間を自己裁量で決められる」のに対し、時差出勤はあらかじめ会社が設定した複数の勤務パターンから選ぶという点で、柔軟性はやや制限される一方、勤怠管理しやすいというメリットがあります。
時差出勤制度の主なメリット
時差出勤制度を導入すると、さまざまなメリットがあります。ここでは、主な内容を3つに分けて解説しましょう。
通勤ストレスの軽減
時差出勤制度の最大のメリットは、通勤ラッシュの回避です。首都圏など大都市圏では朝夕の電車・バスが非常に混雑しており、毎日それに巻き込まれることが従業員の大きなストレス要因となっています。
始業時間を1〜2時間ずらすことで混雑ピークを避け、心身の疲労を軽減できます。疲労軽減は集中力向上にもつながり、業務効率アップも期待できます。
ワークライフバランスの向上
育児や介護、通院など家庭の事情を抱える従業員にとっても、時差出勤制度は大きな助けになります。たとえば、子どもを保育園に送ってから出社する、親の通院に付き添ってから午後から出社するなど、ライフイベントと仕事を両立しやすくなります。
働き方の多様化が叫ばれている現在、このように個人の生活スタイルに合わせやすい制度は、従業員満足度の向上や離職防止にもつながります。
多様な人材の確保と定着
時差出勤制度は、企業が多様な人材を確保・定着させるうえで非常に有効な施策です。近年は働き手の価値観が多様化しており、育児や介護といった家庭責任を担う人や、自己成長やプライベートの充実を重視する若年層など、従来型のフルタイム勤務では働き続けにくい層が増えています。
時差出勤を導入すれば、保育園の送迎や家族の通院といった日常的な用事と仕事を両立しやすくなり、安心して長期的に働ける環境を整えられます。また、企業側にとっても人材の選択肢が広がり、優秀な人材を逃しにくくなる効果があります。そのため、ダイバーシティ推進や人材確保戦略の一環として制度を導入する企業が年々増加しているのです。
時差出勤制度のデメリット
時短出勤制度は、メリットだけではなくデメリットもあります。導入を検討する前に、自社にどんな不利益が生じるのか、事前に把握しておきましょう。
コミュニケーション不足のリスク
勤務時間帯がずれることで、チーム内の顔を合わせる時間が減り、情報共有がしにくくなる可能性があります。特に、チームワークが求められる業務では連携不足による生産性低下やトラブルにつながるおそれがあります。
コミュニケーション不足を解消するためには、全員が顔を合わせる時間を設けるのが重要です。コアタイムを設ける、定例ミーティングをオンライン化するなどの工夫が求められます。
勤怠管理が複雑になる
時差通勤を導入すると、従業員ごとに始業・終業時刻が異なります。すると、勤怠管理や残業時間の算出が複雑になります。
紙ベースや旧式システムでは人的なミスが起こりやすく、対応も困難です。従業員数が多い場合は、勤怠管理システムの導入・設定変更が必要になるケースもあるでしょう。
就業規則の整備が必要
制度導入にあたっては、就業規則や労使協定などの整備が不可欠です。始業・終業時刻、対象者、手続き方法、賃金・休憩・時間外労働の扱いなどを明確に規定し、従業員に周知する必要があります。
特に、深夜勤務や一斉休憩の除外などは労働基準における要件に注意が必要です。
利用率が上がらない可能性
制度があっても、申請手続きが煩雑だったり、周囲に遠慮して使いづらい雰囲気があると、実際にはほとんど利用されないという場合も。周知が徹底されていなければ、制度自体があることを知らないケースもあります。
導入する前には、必ず従業員のニーズ調査を行いましょう。導入後も定期的に利用状況を確認して改善していく姿勢が重要です。
時差出勤制度を導入するステップ
制度を導入し、成功に導くためには、いくつかのステップが必要です。ここでは、具体的な流れについて解説します。
- 導入目的と対象範囲を明確化する…自社が時差出勤制度を導入する目的を明確にします。通勤混雑の回避、従業員満足度向上、人材確保、感染症対策など、目的を定めることで対象範囲(全社員か一部部署か、期間限定か恒常制度か)も決めやすくなります。
- 時間帯や運用ルールを設計する…始業・終業時間の幅をどの程度にするか、どのパターンを用意するかを検討しましょう。たとえば「8時・9時・10時始業」の3パターンなど複数の勤務帯を用意する方法が一般的です。また、事前申請制にするか、日ごとに選択できるかなど、運用ルールも定めます。
- 就業規則・勤怠管理体制を整備する…制度内容を就業規則に記載し、労使協定が必要な場合は締結します。同時に、始業・終業時間が複数ある状態でも正確に勤怠管理ができるよう、システム設定や管理体制を整備します。
- 従業員への周知と教育…導入前に制度の目的やルールを丁寧に説明し、利用イメージが湧くようにFAQやモデルケースも用意します。管理職にも研修を行い、適切な運用を促す体制を整えます。
- 運用と改善…導入後は、利用率や従業員の声を定期的に収集し、制度が目的に合致しているかを検証します。必要に応じて時間帯や申請手順の見直しを行い、制度をブラッシュアップします。
制度は運用しはじめたら終わりではなく、定着するまでには時間がかかります。改善ポイントを随時洗い出し、従業員が利用しやすいように随時仕組みを整えていきましょう。
まとめ
時差出勤制度は、通勤ストレスの軽減やワークライフバランスの向上、多様な人材の確保・定着に貢献する一方で、コミュニケーション不足や勤怠管理の複雑化といった課題も抱えています。制度を成功させるためには、導入目的や対象範囲を明確にし、就業規則や勤怠管理体制を整備したうえで、従業員への丁寧な周知・教育を行うことが重要です。
さらに、導入後も利用状況や現場の声を継続的に収集し、制度を改善していく姿勢が求められます。制度を確立させ、従業員の満足度の向上へつなげていきましょう。